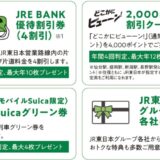資金調達データ
- 配信日2025年9月11日 08時00分
ニュースの概要
ナッジ株式会社は、次世代クレジットカード「Nudge」において、国内初のステーブルコイン「JPYC」での支払い受付を2025年10月を目指して開始することを発表しました。この取り組みにより、世界中のVISA加盟店でJPYCを使用して決済が可能になります。JPYCは日本円に連動するため、ユーザーは価格変動のリスクを低減しつつ、一定の価値を持つデジタル通貨で取引ができるようになります。今回のサービスは、従来のクレジットカード払いをステーブルコインで行う新しいモデルを提供し、決済の幅を広げることを目的としています。
新商品・新サービスの特徴・売り・競合商品との違い
新商品の「Nudgeカード」は、柔軟な決済システムを基盤としており、JPYCを使用した返済機能が新たに追加されました。この返済方法では、ナッジ指定のウォレットアドレスにJPYCを送金することで返済ができ、すでに利用可能な「セブン銀行ATM払い」や「銀行振込」と並んで新しい選択肢が増えます。
競合他社のクレジットカードサービスと異なる点として、Nudgeカードは“いつでも好きなだけ返済”という独自の返済オプションや、ステーブルコイン払いを提供することから、利用者により多様な金銭管理方法を提供します。また、手続きが簡素化され、多くの店舗で利用できるVISA加盟店の広範なネットワークを活用できるため、広義なデジタル決済環境を提供するという利点があります。
他のステーブルコインと比較すると、JPYCは日本円に完全に補完されているため、為替リスクを気にせず安定した価値で取引ができ、それが提供される経済圏で特に強力な選択肢となります。
新商品・新サービスがおすすめの方
新しい「Nudgeカード」のJPYC払いは、特に以下の方々におすすめです。
-
デジタル通貨に関心がある法人経営者
ステーブルコインを用いた支払いを行うことで、取引の透明性や効率性を向上させたい法人のお客様にとっては、大きなメリットを享受することができます。 -
財務管理を効率化したい経理担当者
歴史的に複雑な通貨オペレーションを簡素化し、より管理しやすい形に変えられるため、経理業務の負担軽減が期待できます。 -
技術革新に興味がある企業
新しい金融技術やプラットフォームを試したいと考えている企業は、JPYC払いを通じて、デジタル金融環境の最前線に立つことができるでしょう。 -
グローバルなビジネスを展開する企業
世界中のVISA加盟店で使用可能で、日本円に連動するステーブルコインの効果を利用すれば、安心して越境取引が行えます。
新商品・新サービスの活用方法
「Nudgeカード」のJPYC払いを活用するための具体的な方法には以下のようなものがあります。
-
コンビニや飲食店での気軽な利用
VSA加盟店であれば、日常の買い物や外食時にJPYC払いを選ぶことができ、従来の現金やクレジットカードに代わる新しい決済手段として利用できます。 -
サブスクリプションサービスの費用支払い
定期的に料金を支払う必要があるサービスに対して、JPYC決済を利用することで、資金の流れを管理しやすくなります。 -
財務の透明性向上
ステーブルコインならではの透明性と取引の記録を利用して、企業の財務状況をリアルタイムで把握することができます。 -
レポーティングの自動化
デジタル通貨を用いた取引は、ブロックチェーン技術によって記録されるため、データの集計やレポート作成を自動化し、業務の効率化に寄与します。 -
クラウドファンディングなどの資金調達
日本円建のステーブルコインは、資金調達の新たな手段ともなり得ます。JPYCを活用して、新規ビジネスやプロジェクトへの投資を容易に行うことが可能です。
このように、ナッジカードによるJPYC払いは、法人経営者や経理・財務担当者にとって、デジタル通貨を利用した新しい業務形態や効率的な財務管理を実現するために大変役立つ手段となります。
ニュースの概要
ナッジ株式会社は、次世代クレジットカード「Nudge」において、日本初となる円建てステーブルコイン「JPYC」での返済受付を2025年10月に開始することを発表しました。このサービスにより、世界中のVISA加盟店においてJPYCを利用したお買い物が可能になります。ステーブルコインは、急速に市場が拡大しており、日本でもJPYC社が資金決済法に基づく登録を完了し、初めての日本円建てステーブルコインとして発行を予定しています。ナッジは、クレジットカードの持つ柔軟な決済システムを活用し、JPYCを用いた後払いシステムを通じて独自の金融体験を提供することを目指しています。
具体的には、ナッジカードの利用者は、JPYCをウォレットから指定のアドレスに送金することでカードの利用代金を返済することができます。この手法は、ユーザーが自分のタイミングで自由に返済できる柔軟性を持っており、特定の条件下で利用対象を拡大する計画もあります。
参考にすべきポイント
このサービスは多くの点で法人経営者および経理・会計・総務・財務担当者にとって重要な示唆を提供しています。まず、ステーブルコインの導入はコスト削減の機会を広げます。特に、海外取引や国際的な業務が多い企業にとって、JPYCを活用することで送金手数料や為替リスクを軽減できます。さらに、取引の迅速化や透明性をもたらし、資金管理の効率が向上します。
また、ナッジカードの柔軟な返済システムは、月々の支払い計画に柔軟性を提供します。これにより、企業のキャッシュフローを効率的に管理することが可能となり、資金繰りの計画に新たな選択肢を提供します。
さらに、ステーブルコインの利用は、企業のデジタル化を促進し、金融の民主化に向けた流れに参加する機会ともなります。新しいテクノロジーやインフラを導入することで、競争力を高めるとともに、顧客に対して新たな提供価値を創出できます。
加えて、JPYCは日本円と1対1の価値を持つため、企業にとって安定した価値基盤を提供します。これにより特に日本国内での利用が容易になり、インフレや為替の変動に悩まされることが少なくなります。ステーブルコインの普及により、将来的にはさらに多くの企業がこの新しい支払い手段を採用する可能性が高まります。
活用する方法
企業がJPYCとナッジカードを活用するためには、まずは自社の業務モデルやキャッシュフローにどのように組み込めるかを検討することが重要です。具体的には、次のような方法があります。
-
ステーブルコインによる支払いの導入
自社取引先やサプライヤーと話し合い、JPYCを利用した取引を推進しましょう。海外取引の場合、JPYCを使うことで為替リスクを軽減し、手数料を削減できます。 -
社内経理システムの整備
ステーブルコインの導入に際しては、経理処理のフローを見直す必要があります。特に、JPYCによる支払いを記録するための新しい会計処理方法を検討することが求められます。 -
教育とトレーニングの実施
ステーブルコインの導入にあたっては、従業員向けの教育が不可欠です。金融リテラシーの向上を図り、デジタル通貨に対する理解を深めることで、効果的な運用が期待できます。 -
マーケティング戦略の見直し
JPYCを利用できることを強調することで、顧客に新たな価値を提供できます。特に、デジタル通貨に対する関心を持つ顧客層にアプローチすることで、新しいビジネスチャンスが生まれる可能性があります。 -
パートナーシップの構築
JPYCを活用する他の企業との協力も重要です。共同マーケティングやプロモーション活動を行うことで、相乗効果を得ることができます。また、技術的なサポートが必要な場合は、JPYC社との連携を通じて専門的なノウハウを取得することも考えられます。
このように、ナッジの次世代クレジットカードとJPYCを通じたステーブルコインの活用は、企業にとって新たな資金管理の選択肢を持つだけでなく、迅速なビジネスの展開や顧客への新しい体験を提供する機会ともなり得ます。デジタル化が進む現代において、これらの技術をいかに活用するかが重要な鍵となります。
次世代クレカ「Nudge」、国内初 (※1) となるステーブルコイン「JPYC」払いの受付をスタート〜 コンビニや飲食店・ネットショップの支払いがステーブルコインで可能に 〜ナッジ株式会社2025年9月11日 08時00分1152ナッジ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:沖田 貴史)は、次世代クレジットカード「Nudge(ナッジカード)」において、JPYC株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:岡部 典孝 以下、JPYC社)が発行を予定するステーブルコイン「JPYC」での返済受付を2025年10月を目処に開始します。これにより、世界約1億5000万店舗超のVISA加盟店において、ステーブルコインでのお買い物が可能となります。
「JPYC払い」対応の背景
ステーブルコインは、世界的に市場が急拡大し、発行総額はすでに2,500億ドル(約42兆円)を超え(※2) 、オンチェーン上での取引量はVisaやMastercardを上回っていると報告されています。(※3) そして、日本では、JPYC社が2025年8月に資金決済法第37条に基づく「資金移動業者」(登録番号:関東財務局長 第00099号)の登録を得て、今秋にいよいよ国内初となる円建てステーブルコインの発行が予定されています。ステーブルコインは金融機関や事業者での幅広い活用が期待される一方、日常生活で広く利用するためには、「利用可能店舗の拡大」と「身近なインターフェースの整備」が不可欠です。サービス開始時点で店舗がJPYC決済を受け付けるには、JPYC社との加盟店契約は不要な一方で、アンホステッドウォレット(※4) の開設や管理など、店舗経営者側に一定の専門知識が求められます。また、大型店・チェーン店では、POSシステムの改修を必要とする場合もあります。こうした状況の中、豊富な加盟店ネットワークを持つクレジッ
出典 PR TIMES